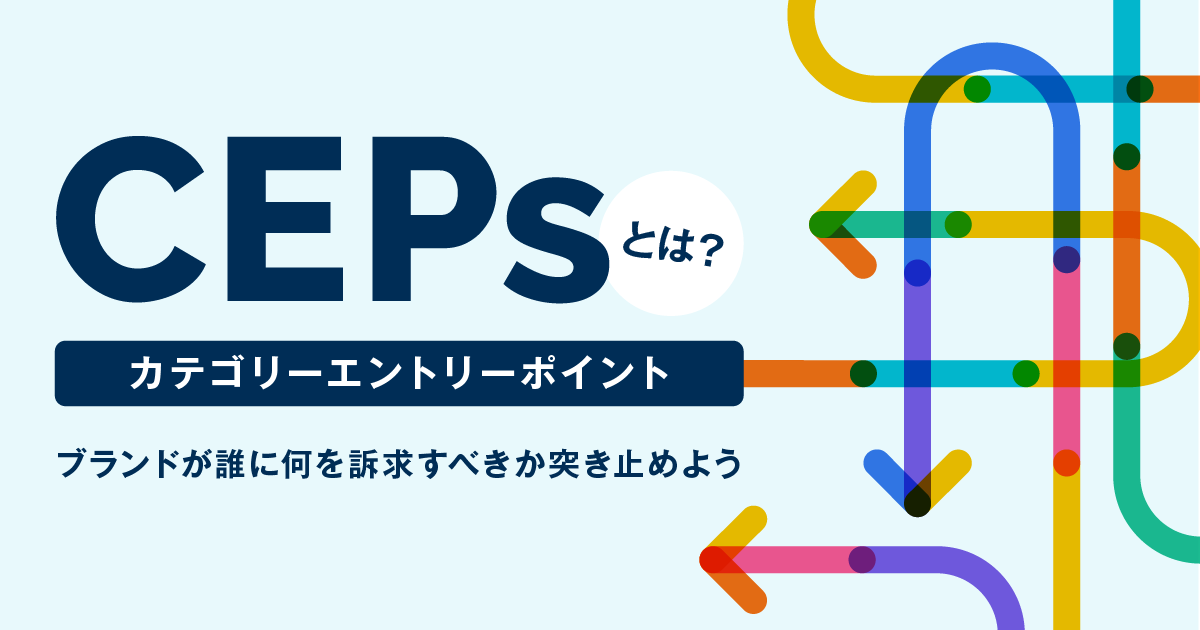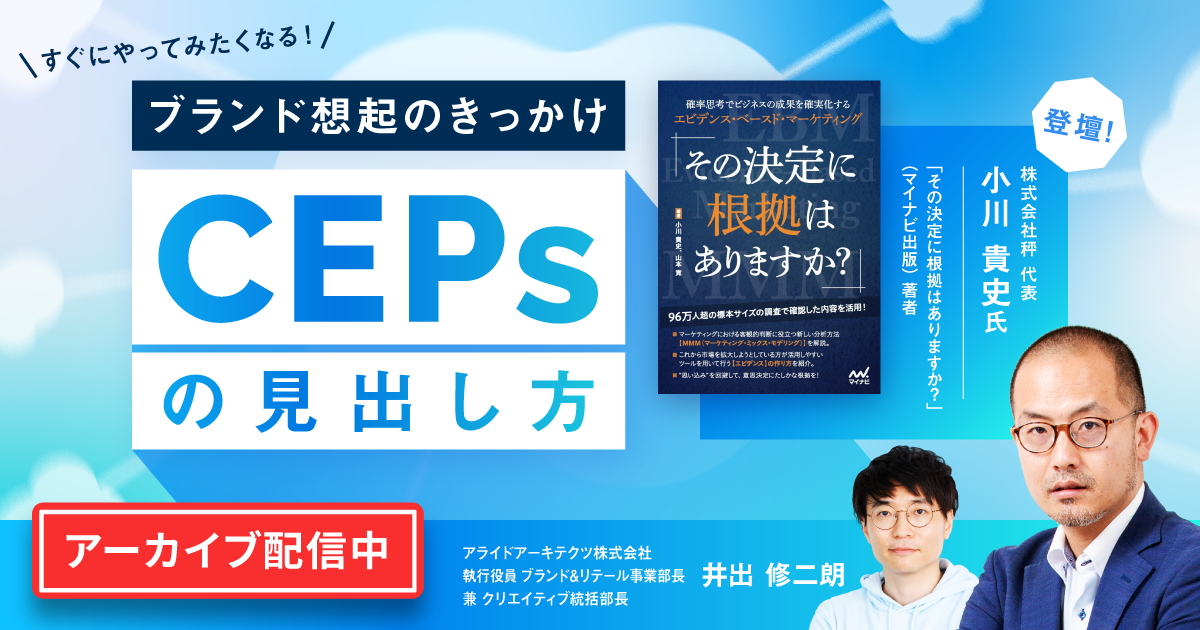老舗食品メーカー「ニップン」の挑戦。顧客理解×一気通貫マーケティングで実現した成果創出プロセスとは

株式会社ニップンは1896年の創業から来年で130周年を迎える、製粉事業、パスタ、冷凍食品、健康食品まで幅広い食品事業を手がける総合食品メーカーです。
2022年から、ニップンの商品をD2Cでお届けする公式通販サイト「ニップンダイレクト」を本格展開。通販限定の冷凍生パスタ&ソースのブランド「nest(ネスト)」や、大人気の冷凍プレート商品の定期便、アマニやサプリメントといった健康食品など、ニップンの技術力を生かした様々な商品を直接お客様にお届けしています。
そんな同社がD2C事業の成長に向けて重視しているのが、顧客の真のニーズを把握したマーケティング戦略の構築です。「Kaname.ax®」による顧客インサイト調査に取り組んだところ、これまでのマスマーケティングや店頭中心の営業・販促からは見えなかったお客様のニーズや利用シーンが明らかになりました。
現在は、広告やLPの改善など、日々のマーケティングの実務から、商品ブランド毎の戦略策定に至るまで、「Kaname.ax®」から提供されるデータを重視し、より深い顧客理解に基づく事業運営を行っています。
今回は、ニップンダイレクト担当の食品事業部門EC事業室の鈴木氏に、顧客インサイト調査から明らかになった新たな顧客理解と、それに基づく施策改善の成果についてお話を伺いました。

大手メーカーが挑むD2C戦略:ニップンダイレクトの2つの目的
ーニップンにおけるニップンダイレクトの位置づけと、大手メーカーとしてD2C事業に取り組む理由について教えてください
鈴木氏:
当社においてニップンダイレクトは、大きく2つの目的を持って展開しています。
1つ目は、小売チャネルではリーチできないお客様との接点を持つことです。通常のスーパーやドラッグストアといった店頭ではなかなか接点が持てないお客様にもアプローチし、ビジネス拡大を図っています。店舗ではなかなか並ばないようなニッチな商品でも、求めているお客様に直接お届けできるのがニップンダイレクトの大きな強みです。
2つ目は、ニップンというブランドや商品に対する顧客エンゲージメントの向上です。当社の商品は温度帯ごとに売り場が分かれるため、例えば「冷凍食品」と「乾麺のパスタ」を、店頭でお客様が同時に認知する機会は限られています。しかしニップンダイレクトであれば、パスタも冷凍食品も健康食品もECサイト上に一気に並べてご案内ができるため、ブランド認知の向上やクロスセルの効果が高まります。

株式会社ニップン EC事業室 鈴木里奈氏
商品開発を機にD2C事業を本格スタート
ーD2C事業への参入のきっかけとなった当時の状況について教えてください
鈴木氏:
D2C領域への参入は、実は商品開発が先行していました。それが、通販限定の冷凍生パスタ&ソースのブランド「nest(ネスト)」です。
価格重視になってしまう量販店向けの商品とは違って、ニップンの技術力やこだわりをしっかりお伝えできる商品を作りたいという想いから生まれました。
ただ、この商品をどのチャネルで売るかを考えた時、スーパーなどの量販店での販売は価格的にも難しいことを考えると、価値をじっくり伝えることができ、それに見合った価格受容性もある直販サイトこそ適しているという結論に至りました。そこで、それまで小規模で運営していた通販サイト(ニップンネットモール)をニップンダイレクトという形に発展させ、人員も補強して本格的に取り組むことにしたのが3年前です。
その後、動物性素材を使わないプラントベースの冷凍プレートシリーズ、オメガ3を手軽に摂取できるアマニシリーズ、サプリメント、粉ものや製菓・製パン材料、乾麺など取り扱いの品数を増やしていきました。2025年5月からは、大人気の冷凍プレート商品10品を毎月お届けする定期便もスタート。開始から順調にお客様数が増加し、現在はニップンダイレクトの主力商品の一つとなっています。

店頭でも大人気の冷凍プレート商品を10個詰め合わせた定期便セット「10個トクトクお届け便」
『お客様が本当に価値を感じているものは何なのか?』─転換点となったUGCとの出会い
ーニップンダイレクト立ち上げ当初は、どのように集客を開始されたのですか?
鈴木氏:
当初はインフォマーシャルがメインでした。番組を制作してテレビ放映の時間帯や番組枠を研究してコンバージョンを追求していました。しかし1年以上経つと効果が薄れてきますし、1回あたりに大きな費用がかかるため、このままこれだけに頼っていて良いのかという課題がありました。さらに電話注文中心のため、お客様との継続的な関係構築が困難でした。
やはりデジタルでお客様を獲得していかないと事業の継続性がないと判断し、デジタルマーケティングに本格転換することにしました。ただ、当時はデジタルマーケティングの知識が不足しており、まさに手探りの状態からのスタートでした。
ー「手探りの状態からスタート」されたのですね。当時の課題について教えてください
鈴木氏:
当初、最も大きな課題は販促メッセージが「手探り」状態であったことでした。
インフォマーシャル中心の時代は、商品を一方的に紹介して電話注文を受けるだけで、お客様がどんな場面で商品を使い、何を評価し、どこに不満を感じているのか——そうした基本的な顧客理解が全くできていませんでした。
そのような状態でデジタル広告運用に取り組みましたが、あくまで私たち企業側が設定した仮説のもとにコピーやクリエイティブを考えている状態であり、本当に必要なお客様にメッセージが届いているのか、魅力が伝わっているのかの手触り感がない状態でした。

この状況を変えるきっかけとなったのが、他社サイトを見ていた時でした。実際に商品を使った方のリアルな声、いわゆるUGCが掲載されているページを見て、商品説明だけのページと比べて説得力が格段に違うことを実感しました。
当社は、素材へのこだわりや、かねてから蓄積してきた技術力によって、お客様に「美味しい」と思っていただける商品をお届けしている自信があります。ただ、企業側がいくら「おいしい」と伝えたところで、生活者の方には伝わりません。納得していただくには、実際に体験した人の声を活用するのが最も効果的だと判断しました。
そこで、UGCサービス「Letro(レトロ)」を提供するアライドアーキテクツ社に問い合わせを行いました。当初はUGCを収集し、そのUGCをLPに活用することでCVRを上げることが目的でしたが、相談を進める中で「そもそもお客様のことをより深く理解する必要があるのではないか」というご提案をいただき、「Kaname.ax®」による本格的な顧客インサイト調査に取り組むことになりました。
「Kaname.ax®」で明らかになった顧客のインサイトとは
ー「Kaname.ax®」による顧客インサイト調査では、どのような発見がありましたか?
鈴木氏:
「Kaname.ax®」による顧客インサイト調査を実施したことで、私たちの想像を大きく覆す発見がありました。
例えば、当初私たち企業側が想定していた冷凍生パスタ&ソースのブランド「nest(ネスト)」のお客様像は、「忙しくて食事を簡単に済ませたいが、美味しい食事を摂りたい方」でしたが、実際は「誰かを喜ばせたいと願う、普段からよく料理をしている方」が多かったのです。「nest(ネスト)」のお客様は楽をしたくて購入しているわけではなく、家族や友人を喜ばせたい、でも自分のレパートリーでは限界がある、外食でしか味わえない美味しさで日々の食卓を豊かにしたい——そんな時の選択肢として活用されていることが分かりました。

通販限定冷凍生パスタ&ソースのブランド「nest(ネスト)」
また、植物性素材だけで作ったプラントベースの冷凍プレートシリーズでは、「コレステロール0」という訴求が効果的だということも判明しました。私たち企業側の立場からは、植物性素材だけで作った商品ですので、「コレステロール0であること」は当然の特徴なのですが、生活者にとっては大きな魅力として映っていることに気づかされました。
これらの調査を通じて、お客様の「奥行き」を感じることができました。マスマーケティングではより広いお客様に一律に届きやすいメッセージでアプローチしますが、ダイレクトマーケティングでは、多様な生活スタイル・価値観を持つ方に刺さる訴求パターンを考え抜くことが重要であると学びました。
「Kaname.ax®」による顧客インサイト調査を行ったことで、商品開発時点では想定していなかった商品利用のきっかけや期待値、「この商品は誰が誰と食べているか」といった具体的な利用シーンが明確になり、お客様により届く訴求の開発や幅出しができるようになったと感じています。
お客様の声を起点としたPDCA体制で成果を最大化
ー「Kaname.ax®」の顧客インサイト調査の結果を受けて、具体的にどのような施策を実施されたのでしょうか?
鈴木氏:
調査結果を踏まえ、大きく2つの施策改善を行いました。
1つ目は、マーケティングメッセージの見直しです。これまで「nest(ネスト)」では「簡単調理」「時短」といった利便性や機能価値を前面に出していましたが、「大切な人との特別な時間を演出する」「レストランクオリティを家庭で」という、体験価値を中心としたメッセージに変更しました。
また、プラントベース商品では「コレステロール0」訴求を強化しました。これまでは当然の特徴として主観的に判断し、クローズアップしてきませんでしたが、、広告やLPで目立つ位置に配置し、健康を意識するお客様に響くコミュニケーションを展開しました。
プラントベース商品の広告クリエイティブの一例。「コレステロール0」という訴求だけでなく、その他顧客調査で明らかになった「カロリー410kcal以下が魅力に思われている」「昼食の置き換えに利用されている」などのファクトに基づき、さまざまなクリエイティブを展開して成果につなげている
2つ目は、ダイレクトマーケティングの全ての顧客接点において、お客様の声を中心に、一気通貫でPDCAを回せる仕組みづくりです。
ダイレクトマーケティングは非常にスピード感が早く、日々お客様のニーズを捉えて高速にPDCAを回し続けなければなりません。
たった1回の顧客調査で得られた学びを目の前の施策に活かして終わるのではなく、常にお客様の声を聞き続けて、マーケティングの戦略策定や、日々の施策に反映し続ける仕組みを持つことが重要だと考えました。
そこで、Kaname.ax®の「ECカートシステムとAPI連携できる機能」を活用し、継続的にお客様の声を取り続ける体制を構築しました。さらに、アライドアーキテクツ社に広告運用からLPの制作・日々の運用(LPO)もお任せすることで、「お客様の声」を中心に一気通貫でPDCAを回すことができるようになりました。
実際に使用しているLPのファーストビュー(2025年9月時点)。広告から中間LP、本LPまでの一気通貫運用により、全ての顧客接点でメッセージの一貫性を確保。各ステップにおける態度変容の役割を明確化し、効果的なPDCAサイクルを実現。
ー「お客様の声」を中心にしたPDCAの仕組みを構築したことで、成果はどのように改善しましたか?
鈴木氏:
プラントベースの冷凍プレートシリーズは、施策実施当初よりCPAが20%改善、広告経由の売上規模も向上しました。また、冷凍プレート「10個トクトクお届け便」は、2025年5月の販売開始から約4か月で目標CPAに到達と好調です。
これは、お客様の声をもとに一気通貫で施策を実行し続けていただいているからこそ得られた成果だと感じています。
顧客調査、広告、LP、UGC…など、それぞれの施策を別のパートナー様にお願いして単発で施策を実行していくと、その分コミュニケーションのコストもかかりますし、ノウハウが蓄積されにくい面があると思います。
アライドアーキテクツ社にはそのすべての過程を一気通貫でやっていただけているため、メーカー側が都度説明をしなくても、当たり前のように「メッセージの一貫性」を担保いただけますし、またクリエイティブの量の担保やPDCAのスピード向上にもつながっています。
そして何より、お客様の声やそれをもとにした施策の結果がノウハウとして蓄積され資産になり、それを基に改善が進められているのが本当に良いと感じています。この体制になる以前は、改善策を考えるときに結局は仮説で考えるしかありませんでしたが、今は根拠をもって進められているため、迷わずに次の打ち手を決定できるようになりました。

お客様と共に歩む、ニップンダイレクトの次なる挑戦
ー今回の取り組みを踏まえ、ニップンダイレクトとしての今後の展望をお聞かせください
鈴木氏:
今回の「Kaname.ax®」の調査で、「お客様を深く理解することの重要性」を実感しました。そして、改めて直販ECをやる意義を感じています。
これからもお客様の声を聞き続けることで、当社商品の隠れた価値をもっと発掘し、必要としていただけるお客様により広く伝えていける挑戦を続けていきたいと考えています。そして、お客様との継続的なつながりを深め、当社商品をより幅広く知っていただく場に育てていきたいです。
記事公開日:2025.11.04

顧客の声を「要」に、マーケティングAXを起動する
Kaname.axは、顧客の声(UGC・VOC*)をAIで解析。マーケティングコミュニケーション設計~実行支援までを一気通貫で支援するプラットフォームです。
顧客の声データとマーケティングコミュニケーション領域の知見をAIで統合・高速分析し、コミュニケーションの起点となるインサイトを発見。施策の実行・検証まで一気通貫で支援します。